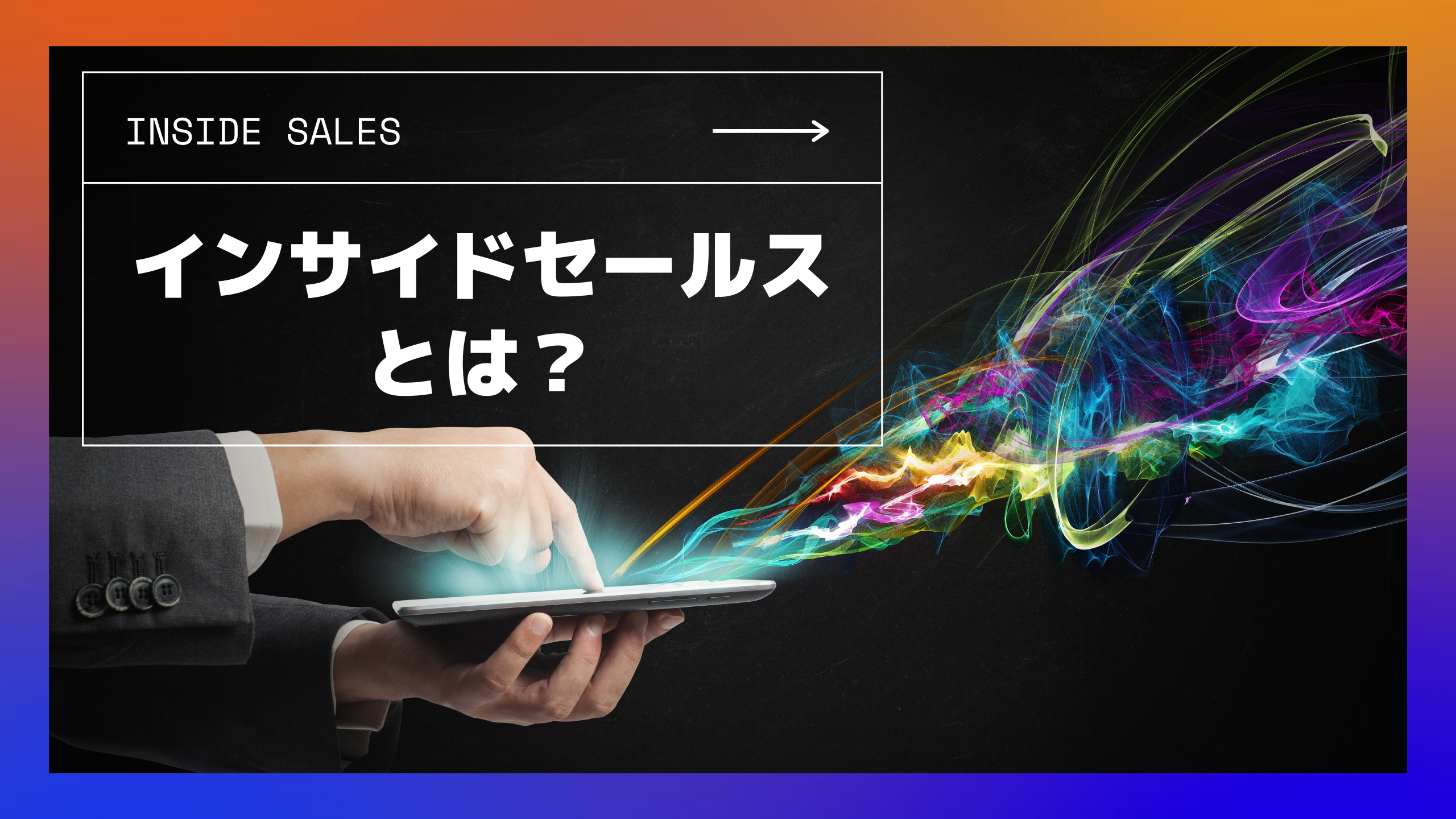
インサイドセールスは、企業にとって顧客獲得のために必要な施策の一つです。
しかし、施策内容がテレアポと同じように受け止められることも少なくありません。
インサイドセールスがうまくいかない企業の多くは、この「テレアポとの違い」への理解度が高くない可能性があります。
この記事では、テレアポとインサイドセールスの違いや、インサイドセールスの運用におけるポイントについて詳しく解説していきます。
目次
インサイドセールスとは何か?

インサイドセールスとは、内勤営業の専門部隊のことを指します。
マーケティングによるリードジェネレーション(見込み顧客の発掘)によって獲得した見込み客に対して、営業のトークスクリプトを使用して電話をかけたり、メールやチャットをしたりして直接アプローチし、見込み顧客の育成「=リードナーチャリング」を行います。
従来型の営業スタイルは、顧客の発掘から受注・その後のサポートまでを1人の営業マンが担当してきました。それに比べ、インサイドセールスは発掘された見込み顧客に対してアプローチをし、自社製品やサービスのファンを増やす作業に徹する専門部隊です。
見込み顧客の購買意欲が十分に高まった段階で、フィールドセールスへリードの情報を受け渡すまでが、インサイドセールスの役割となります。
さらに詳しく
インサイドセールスとテレアポの違いとは?

テレアポとインサイドセールスには、目的に明確な違いがあります。
ここでは、テレアポとインサイドセールスの役割や目的の違いについて、解説していきます。
- 目的が違う
- 得たい成果が違う
- 成果を得るまでの時間が違う
目的が違う
テレアポの目的は「アポの取得」であり、インサイドセールスの目的は「見込み顧客の育成(リードナーチャリング)」という明確な違いがあります。
テレアポは、テレフォン・アポイントメント(telephone appointment)を略した言葉であり、その名の通り電話でアポを取得することが役割です。
テレホンアポインターは、与えられた顧客リストの上から順に電話をかけていき、自社商品やサービスの説明をしてアポを取得します。
その後、アポがとれた顧客へ営業が訪問して商品やサービスの説明を行い、興味が湧いた顧客へは数回訪問したのちに提案、受注へとつなげていきます。
一方、インサイドセールスは、見込み顧客を育成することが目的となります。アポを取ることだけが役割ではありません。
展示会やセミナー、DMなどのマーケティングによって得られた見込み顧客へ、決められたトークスクリプトにより直接電話をかけ、自社製品やサービスの紹介をします。
もし、顧客がまだ情報の収集中などで購買にはまだ時間がかかる様子の場合、無理にアポを取得しようとしません。
その顧客が商品に興味がわくまで、適切なタイミングで有益な情報が記載されたDMやメールマガジンを送ったり、展示会やセミナーの案内を送ったりして、購買意欲を高めるための活動=リードナーチャリング(見込み顧客の育成)を行います。
見込み顧客の購買意欲が高まるまで育成すること=「リードナーチャリング」こそが、インサイドセールスの役割であり目的です。
得たい成果が違う
テレアポとインサイドセールスの役割や目的が異なるということは、得たい成果も違ってきます。
テレアポはアポを取得することが目的なので、成果目標は「アポを取得した数」となります。
一方、インサイドセールスの場合は単純にアポを取得した数とはなりません。
なぜなら、インサイドセールスの目的はリードナーチャリング(見込み顧客の育成)なので、購買意欲が高まった顧客の数=ホットリードの数=案件化できた数が成果目標(ゴール)となります。
ここで注意したいポイントが、インサイドセールスの成果として「アポを取得した数」を重要視してはならないことです。
なぜかと言うと、アポイントの数を重要視してしまうとアポを取ることが目的となってしまい、そればかりを追いかけて本来の目的であるリードナーチャリングの役割を担えないインサイドセールス部隊となってしまうからです。
そうなってしまうと、テレアポ部隊と変わらない部隊となってしまいます。
成果を得るまでの時間が違う
インサイドセールスは、見込み顧客の購買意欲が高まるまでナーチャリングすることが役割です。したがって、テレアポのように「ホットリードではない見込み顧客」のアポがとれても成果には繋がりません。
したがって、両者には成果を得るまでの時間がまったく異なってきます。
ここに、目的や成果、またゴールまでの時間と大きくわけて3つの異なるポイントがあるのです。
そのため、上述したようにインサイドセールスのよくある失敗例で、早く成果が欲しいがためにアポの数を重要視してしまうことにつながるのです。
したがって、会社としてインサイドセールスの成果には時間がかかるため、見込み顧客がホットリードとなるまでの育成のプロセスごとにKPIを設定することが、インサイドセールスの成功につながります。
インサイドセールス運用の課題

ここでは、インサイドセールスの運用における課題について詳しく解説していきます。
- ツール運用ができる人材の確保
- KPIへの共有のズレ
- 顧客育成の時間
ツール運用ができる人材の確保
インサイドセールスの業務は、さまざまなツールを使用します。単純に、電話やメールだけではありません。
たとえば、SFA(Sales Force Automation)や、MA(Marketing Automation Tool)などがあげられます。
SFAとは、営業支援ツールです。案件の情報や顧客情報などを蓄積・管理・共有するツールです。
見積もりの申請や承認、リアルタイムでの案件情報の閲覧が可能なため、営業業務の効率化や、他部署への早急なる情報共有が可能となります。
MAとは、マーケティングを行う企業では最近導入する企業が増えてきています。
一連のマーケティング活動において、見込み顧客の情報の管理や、現在どのステータスにある見込み顧客なのかなどを管理・把握したり、他部門と共有したりするために活用されるツールです。
インサイドセールスでは、これらのツールを駆使して業務を行うため、このようなツールを使用することに拒否反応がある人には、業務の担当は難しいでしょう。
したがって、ツールを使用しながら業務の遂行が可能な人材の確保が必要となってきます。
さらに詳しく
KPIへの共有のズレ
アポを取得した数をKPIとするテレアポとは違い、見込み顧客を育成することが大きな役割であるインサイドセールスは、アポの数のみをKPIにすると成功しません。
なぜなら、アポ取得数に重きをおいてしまうと、顧客の育成に時間がとれなくなってしまうからです。
成果を早くあげたいがために、どうしても時間の掛からないアポを取得することに時間をかけてしまい、ホットリードでもない見込み顧客の情報をフィールドセールスへパスするようになってしまいます。
その後、パスされた顧客情報をもとにフィールドセールスが客先へ訪問しても、「まだ成約するには予算化もされていなく、受注までには2年以上かかる」という結果となってしまいます。
これでは、内勤営業であるインサイドセールスと、外勤営業のフィールドセールスへ分業した意味がなくなってしまいます。
分業はあくまで、インサイドセールスがリードをホットリードへ育て、受注確度が高くなった顧客情報(案件化した情報)をフィールドセールスへパスし、詳細な説明および提案後に、すぐ受注へむすびつけることが目的です。
業務の効率化を図るための営業プロセスの分業なので、案件化されていない情報をいくらパスしても非効率、かつ本末転倒です。
またこれが、部門間の対立を生んでしまうという、インサイドセールス導入におけるもっとも多い失敗例となります。
顧客育成の時間
インサイドセールスの目的である見込み顧客を育成するまでには、時間がかかります。
インサイドセールスのKPIをアポの数だけに設定する、もしくは重要視してしまっては失敗につながります。
なぜなら、成果をあげるためにアポの数だけを追いかけてしまっては、本来の役割である「見込み顧客の育成」ができなくなってしまうからです。
最近、「インサイドセールスのメンバー募集」などの転職サイトを介して企業に採用され、実際に業務に従事してみると「実態はテレアポ業務であった」などという口コミも増えてきました。
このように、インサイドセールスを採用する企業は年々増えてきているものの、会社によっては「本来のインサイドセールスの役割として機能していない」ケースも散見されます。
そして、やはりインサイドセールスの導入は断念しよう、という最悪の結果を招くケースもあります。
そうならないためにも、時間はかかりますがインサイドセールス本来の目的である「見込み顧客の育成」からブレないことが非常に重要です。
インサイドセールスで成果を出すためのポイント

ここでは、インサイドセールスで成果を出すためのポイントを解説していきます。
- SFAの導入
- SFAツールを運用できる人材育成
- 他部署との共有をする仕組み作り
SFAの導入
上述したように、インサイドセールスの導入を成功させるためには、ツールを活用することが必要不可欠です。
中でも、SFA(営業支援システム)は、リードジェネレーションで見込み顧客を獲得してからリードナーチャリングを行い、フィールドセールスが客先へ訪問して提案・受注までのすべての営業情報が一元管理されます。
マーケティング部門がリード(見込み顧客)を獲得後、どこで?どんな方法で獲得したリードなのか?何の展示会で?といった情報をすべて蓄積・共有できます。
したがって、その情報をもとにインサイドセールスが電話などによってリードへアプローチして、契約の時期や、予算化の時期などをヒアリングします。定期的なヒアリングやセミナー、展示会の情報提供を行ってナーチャリングを行います。
インサイドセールスがヒアリングした内容をSFAへ蓄積し、フィールドセールスとその情報を正確に連携することで効率よく受注へとつなげられるのです。
SFAツールを運用できる人材育成
SFA導入が不可欠なインサイドセールスですが、そのためには働くスタッフがSFAツールを使えるように育成しなくてはなりません。
インサイドセールスは、SFAの情報をもとに他部署と情報をリアルタイムで共有することで、業務の効率化を図ります。
また、SFAに蓄積された過去の営業情報をもとに、新人の教育にも使用されます。
SFAは営業ノウハウの宝庫です。過去の先輩が蓄積した見込み顧客へのヒアリングの内容や、どんなタイミングでリードの情報をフィールドセールスへパスしたかなどの「営業ノウハウ」が詰まっています。
したがって、その情報をもとに新人や中途で採用した社員への人材教育をSFAを使って実施します。
さらに詳しく
他部署との共有をする仕組み作り
インサイドセールス導入の最大の目的は、営業業務の効率化による会社全体の売上の最大化です。
従来型の、すべての営業プロセスを1人の営業マンが実施するのではなく、顧客の発掘、顧客の育成、受注業務をそれぞれの部隊へ分けることで営業業務の効率化をはかるというものです。
したがって、それぞれの専門部隊の間で情報の共有を正確かつスピーディーに実施しなければなりません。
最終目標である会社の売上の最大化を実現するためには、SFAの機能をフルに活用し、他部署との情報の連携を速やかに行うことが非常に重要となってきます。
また、SFAを使用することで業務の効率化をはかり、最小限の人材で目標の達成を目指します。
まとめ

テレアポとインサイドセールスには、業務における目的や役割に明確に違いがあります。
インサイドセールスでKPIの設定をあやまってしまうと、テレアポの専門部隊となってしまい、よくあるインサイドセールス導入の失敗ケースとなってしまいます。
そうならないためには、インサイドセールスの真の目的であるリードナーチャリングに重点をおき、見込み顧客育成の専門部隊であることをしっかり意識することが重要です。
また、完全なホットリードをフィールドセールスへパスできるプロ集団へと作り上げることが必要になってきます。
オフラインマーケティングや営業施策に課題を感じている企業様を対象に、オンライン個別相談会を実施中!

結果が出るオフラインマーケティング施策についての無料オンライン相談会を企業の状況に行った形で行なっておりますので、「これまで結果が出てこなかった」、「どの施策を行えばいいか」などの悩みを持つご担当者様は、お気軽にご相談ください。

